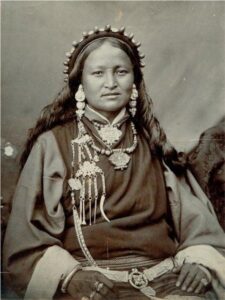チベット仏教を象徴する道具のひとつに「マニ車(マニぐるま)」があります。
円筒状の筒を軸に取り付け、手で回転させるだけのシンプルな形。
けれどその中には深い祈りと智慧が込められています。
この記事では、マニ車の歴史、意味、使い方、そして現代での活かし方について解説していきます。
マニ車の歴史と起源
マニ車は、インドからチベットに仏教が伝わった8世紀ごろに登場したとされています。
当時、経典の多くは膨大で、すべてを読誦するのは一般の人々には難しいものでした。
そのため、経文を「書く」「回す」といったシンプルな形で祈りを実践できるように工夫されたのです。
チベットの僧院や村では、道沿いや寺院の入り口に大小さまざまなマニ車が並べられ、誰でも自由に回すことができます。
巡礼者はその前を通るときに手で一つひとつ回し、祈りを重ねていきました。
マニ車の構造
マニ車の外観はシンプルですが、その内部には大切なものが納められています。
- 筒の中身
経文(主に「オム・マニ・ペメ・フム」の真言)が何千、何万回も書き写された紙が収められています。 - 回転の意味
筒を一回転させると、内部の経文をすべて唱えたのと同じ功徳が得られるとされています。 - サイズの違い
大きなものは寺院に設置され、小型のものは家庭用や携帯用として普及しました。
マニ車に込められた祈り
最もよく納められる真言(マントラ)は「オム・マニ・ペメ・フム」。
観音菩薩を象徴するこの真言は、「慈悲」「浄化」「悟り」を意味し、唱えることで心が清められるとされます。
マニ車を回すという行為は、単なる物理的な動作ではなく、「祈りを動かす」行為そのもの。
その回転は、自分だけでなく周囲の人々や世界全体に祈りを広げていく力があると信じられています。
「オム・マニ・ペメ・フム」の真言(マントラ)についてはこちらの記事で解説しています。

マニ車の使い方
基本的な作法
- 右手で持ち、右回り(時計回り)に回転させるのが基本。
- 回しながら「オム・マニ・ペメ・フム」と心の中で唱えるとより効果的。
どんな時に使う?
- 瞑想や祈りの時間に
- 不安を感じたときの心の安定に
- 誰かの健康や安全を願うときに
自宅での取り入れ方
小型のマニ車は机や仏壇に置いて使うことができます。
1日の始まりや終わりに回すことで、気持ちを整える習慣となります。
現代におけるマニ車
現代社会では、マニ車は単なる宗教道具ではなく「心を整えるツール」として注目されています。
- マインドフルネスとの共通点
呼吸や意識を整える瞑想法と同じく、マニ車を回すことで「今この瞬間」に集中できます。 - インテリアとしての存在感
真鍮や銅で作られたマニ車は、空間に神秘的で落ち着いた雰囲気をもたらします。 - 世界的な広がり
欧米でもヨガや瞑想のシーンで取り入れられ、宗教を超えて「祈りを感じる習慣」として広がっています。
マニ車を使った瞑想の方法についてはこちらの記事で解説しています。

よくある質問(FAQ)
Q. マニ車は誰が使ってもいいの?
はい。宗教や国籍に関わらず、誰でも回すことができます。祈りの行為は普遍的なものだからです。
Q. 自宅で回すだけでも効果はある?
あります。小さなマニ車でも、中に経文が納められていれば十分に祈りの力が宿るとされます。
Q. 回す方向に決まりはある?
基本は時計回りです。これは太陽の動きや宇宙の循環に合わせる意味があるとされています。
TIBET INORIとマニ車
TIBET INORIは、チベットの人々が大切にしてきた「祈りの道具」としてのマニ車を、現代の暮らしに届けています。
それは単なる装飾品ではなく、あなた自身が祈りを感じ、心を整えるための小さな相棒。
- 静かに一人で回す時間
- 家族の健康を願って回すひととき
- 友人に贈る「祈りのギフト」
マニ車は、時代や文化を超えて「祈りをつなぐ存在」です。
あなたの暮らしにも、その静かな回転を取り入れてみませんか。
TIBET INORI 公式オンラインストア
🕉️ マニ車を実際に手に取ってみませんか?
TIBET INORIのオンラインショップでは、祈りを込めて作った
本格的なマニ車を取り扱っています。