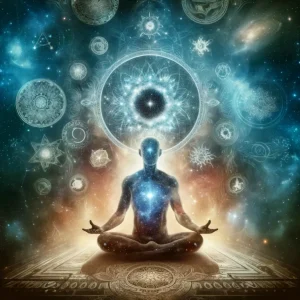チベット仏教の巡礼や修行でよく目にするのが、全身を地面に投げ出すように礼拝する姿です。
これが 五体投地(ごたいとうち) と呼ばれる修行法であり、信仰を象徴する大切な実践です。
この記事では、五体投地の意味や方法、歴史的背景、日常生活における意義を解説します。
五体投地とは何か?
五体投地とは、両手・両膝・額の「五体」を地面につけて礼拝する方法です。
- 五体:両手、両膝、額
- 動作:立った状態から全身を地面に投げ出し、五体を地につけ、再び立ち上がる
- 意味:自我を捨て、仏・法・僧(三宝)や菩薩に身心を捧げることを表現
単なる礼拝動作ではなく、自己を明け渡す謙虚さと、祈りの誠を示す行為なのです。
チベット仏教における五体投地の意義
チベット仏教では、五体投地は信仰の根幹に関わる実践とされています。
- 自己を空にする修行
身体を地面につけることで、傲慢さを手放し「空(くう)」の境地を体感します。 - 功徳を積む
五体投地を繰り返すことで善行が積まれ、悟りへの道が開けると信じられています。 - 巡礼の実践
聖地巡礼では、何百キロもの道のりを五体投地で進む修行者もいます。
チベット仏教と巡礼については、こちらの記事で詳しく解説しています。

五体投地の方法
五体投地は大きく分けて次の手順で行われます。
- 胸の前で合掌し、祈りを唱える
- 手を頭の上に上げ、仏への帰依を示す
- 両手を地につき、全身を投げ出す
- 額、両手、両膝を地面につける
- 立ち上がり、再び祈りを捧げる
この一連の動作を繰り返すことで、祈りと修行が深まります。
巡礼と五体投地
チベットやラサのジョカン寺、カイラス山などの聖地では、巡礼者が道中ずっと五体投地を繰り返しながら進む光景が見られます。
- 距離:数百kmを何ヶ月、何年もかけて行う修行者もいる
- 意義:一歩一歩を祈りとともに進むことで、信仰を全身で表現
- 象徴性:極限の苦行を通して、心の純粋さと信仰を深める
日本仏教との比較
日本の仏教にも合掌や礼拝はありますが、五体投地のように全身を投げ出す礼拝は一般的ではありません。
- 日本仏教:合掌・礼拝が中心(立礼・座礼)
- チベット仏教:五体投地によって身体を通じた祈りを重視
この違いは、信仰表現のスタイルの差を示しています。
TIBET INORIでは、ロゴマークに合掌を採用しています。
チベット仏教における合掌は、単なる「祈りのポーズ」ではなく 「尊敬・信仰・謙虚さを全身で表す入り口」 という意味があります。
なので、「祈り」や「つながり」をテーマにしたTIBET INORIのロゴマークは合掌をモチーフにしています。
五体投地と現代の意味
現代社会においても五体投地は、単なる宗教的行為ではなく「心を整える実践」として注目されています。
- 自己を見つめ直す時間
- 心身の浄化とリセット
- 感謝と謙虚さを取り戻す方法
五体投地は「祈りのヨガ」とも言える実践であり、精神的な癒しにもつながります。
よくある質問(FAQ)
Q. 五体投地をどこで体験できますか?
チベット仏教の僧院やリトリート、ダラムサラやネパールの寺院で体験できます。
Q. 五体投地を自宅でもできますか?
はい。小さなスペースでも簡易的に実践可能です。祈りの心を込めることが大切です。
Q. 何回くらい行えばよいですか?
明確な決まりはありませんが、修行者は数百回から数千回を行います。日常では数回から始めても効果があります。
TIBET INORIと五体投地
TIBET INORIは、五体投地が象徴する「祈りと謙虚さ」を大切にしています。
- 身体を通じて祈る文化
- 巡礼に込められた信仰の力
- 謙虚さと感謝を実践する心
五体投地は、祈りを形にする最も純粋な実践のひとつ。
その精神を、現代の日常にも届けていくことがTIBET INORIの願いです。